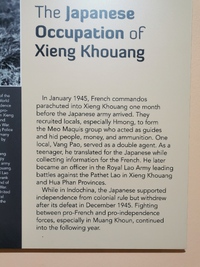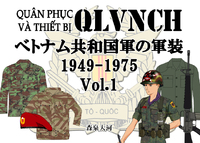2021年11月25日
コルト.45
※2021年11月26日更新
塗装前

買った当時、金と手間をかけずに金属感を出そうと、本体は塗装せず、単に銀色のプラモデル用塗料をティッシュに含ませて擦り付けたのですが・・・
本当にただ、プラスチックの上に塗料を乗っけただけって感じ。それにランヤードリングもプラ製なので折れてなくなってしまいました。
しかし僕のメインの趣味であるリエナクトではピストルを持つ機会がほとんど無いので、こんな状態でも困ることはなく、長年放っておいてしまいました。
それが先日、初めてインディのパーカーシールを使ってグリースガンやMAT-49を塗装してみたところ、手軽にリアルなスチールの質感を出せることが分かったので、これを機に手持ちのトイガンを次々再塗装しだしました。
そして今回塗ったのが、僕が持ってる唯一のピストルであるM1911A1。ついでにランヤードリングもステンレスの針金で復元。
ちなみに塗装する際、はじめてこのトイガンを分解したのですが、写真を撮らずに部品をバラバラにしたら戻し方が分からなくなり、ちょっと困りました。そこでネットで検索して見つけたこちらの記事(misoのレビュー様)を見ながら、どうにか元に戻す事ができました。
塗装後


下地はミッチャクロンマルチを塗っただけでシルバー系は塗っていませんが、それでも表面をスポンジヤスリで擦ると、こんなに金属っぽくなりました。
この部分だけ見ると、とても定価2,000円以下のエアコキ(スプレー代より安い)3,000円強とは思えない仕上がり。塗ってよかった!
1911系ピストルの呼び方
ところで、実は僕、米軍のM1911ピストルが『ミリガバ』と呼ばれていることをつい最近知りました。最初聞いたときは何のことかわからなかったです。
しかしミリガバって、考えれば考えるほどおかしな言葉。
【ミリガバ誕生の流れ】
米軍がコルトの新型45口径自動拳銃を採用、制式名称『M1911』を付与。
↓
コルトがM1911の民間仕様を発売する際、政府採用である事をアピールするため、商品名を『ガバメント(Government)』とする。以後、コルトは『民間向け1911シリーズの中で、M1911に準拠したフルサイズ・スタンダード仕様』をガバメントと呼称する。
↓
これを米国の銃器ユーザー・マニアが、『M1911を含む』スタンダード仕様の別名がガバメントであると拡大解釈。
↓
さらに日本の遊戯銃ファンが、M1911を『ガバメントの軍用仕様=ミリタリーガバメント』と呼ぶようになる。
この流れを考えると、ミリガバという言葉は『軍用拳銃の民間仕様の軍用仕様』という、滑稽な意味になりますね。
現在でも製造元のコルトがガバメントと呼称するのは1911シリーズの中でもスタンダード仕様のみであり、それ以外の1911シリーズはガバメントとは呼ばれません。
まして米軍向けに生産されたM1911は本来、ミリガバどころか、ガバメントですらないのです。

じゃあ『ガバメント』以外でM1911や1911シリーズを何と呼ぶべきか?
僕の感覚では、米軍のM1911に関しては、わざわざ別名など使わず、そのまま「M1911 (エム・ナインティーンイレブン)」と呼べばいいじゃんと思います。それが唯一にして絶対の正式名称なんですから。
とは言え、英語への憧れと劣等感が同居している日本の事。「ナインティーンイレブン」なんて言ったら、カッコつけだと笑われそうと心配なら、「いちきゅういちいち」と言う手もあります。野暮ったいので僕は好きじゃないけど。
「11.4mm拳銃」?そりゃ自衛隊だけじゃ。
一方、総称である1911シリーズM1911を含むスタンダード仕様あるいはフルサイズの1911シリーズに関しては、世間への浸透度も高く語呂も良い適切な別名があります。
それが『コルト.45』。シングルアクションアーミーと区別するため『コルト.45オート』とも言います。
読み方は「コルト・フォーティーファイブ」でも良いですが、「こると・よんじゅうご」でも、昔の映画っぽくてカッコいい。(私見)
このコルト.45は映画だけでなく、実銃の世界でも(場合によってはコルト製以外も含む)1911シリーズ全体
M1911もガバメントもデトニクスもハイキャパも、みんなコルト.45。これで世の中丸く収まるじゃないですか。
2021年11月25日訂正:
『コルト.45』と呼ばれるのは基本的にはスタンダードまたはフルサイズ仕様のみで、短縮版など他の仕様の1911シリーズは含めないようですね。僕の勘違いでした。失礼しました。
おまけ
M1911と並行して、これまたいにしえのマルシン製非ブローバックガス式?M1カービンも塗りました。
塗装前

塗装後



ストックも塗りましたが、今回は工程簡略化(要は手抜き)の実験として、オイルではなく水性ニス(オールナット色)を使ってみました。
刷毛でさっと塗るだけなので非常に楽チンでしたが、ニスは木材に染み込むのではなく表面を樹脂の層で覆うだけなので、塗りムラが樹脂の塊になってしまいました。
それでもよく見なければ分からないレベルなので、水性ニスは工程が楽で仕上がりはそこそこといった感じ。ちょっとした木材を塗るには良いと思います。
しかし樹脂の塊が生じやすく、重ね塗りしてもそれを隠すことが難しいので、思い入れのある銃に使うにはリスクが高いですね。
次はM1ライフルを塗ろうと思いますが、そのときはちゃんとオイルステインを使おうと思います。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。