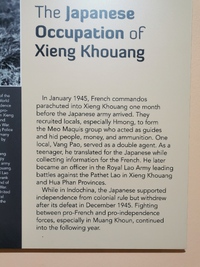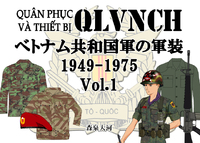2025年05月03日
4月の撮影会&空挺師団のヘルメット
4月末に少人数で撮影会を行ってきました。
空挺師団では1960年代末以降、迷彩塗装されたヘルメットが標準装備となりました。





設定はベトナム戦争末期(1972~1975年頃)のベトナム陸軍空挺師団です。
空挺師団では1960年代末以降、迷彩塗装されたヘルメットが標準装備となりました。
なので僕は中国製の安いM1ヘルメットのレプリカに自分で迷彩柄を塗装して使っています。

▲1971年南ラオス戦役(ラムソン719作戦)終了後の空挺師団の式典

▲今回の撮影で使った僕の自作品(過去記事『4代目迷彩ヘルメット』参照)
まだ満足いっていないので、そのうち5代目を製作したいと思います。
なお迷彩柄は師団として統一されているわけではなく、部隊によってかなりバリエーションがあるので、上記はほんの一例です。
また1972年頃には作戦服と同じパステルリーフ柄の国産ヘルメットカバーが導入され、エリート部隊を中心に徐々に使用が広がっていきます。
ただし全将兵に行き渡るには至らず、1975年の時点でも空挺師団の多くの部隊では迷彩塗装ヘルメットが使われていました。
▲パステルリーフ生地ヘルメットカバーの使用例 (1975年1月)

▲我が家のパステルリーフ生地ヘルメットカバー(実物)
ちなみにベトナム海兵隊の制式装備として1960年代初頭に導入され、その後陸軍の一般部隊でも普及した米国製のリバーシブル式カモフラージュ(所謂ミッチェル)ヘルメットカバーですが、これは空挺師団ではほとんど使用されませんでした。
着用率で言えば、エリートの空挺師団よりも、ほとんど民兵に近い地方軍の方がよっぽど多くのミッチェルヘルメットカバーを使っています。
なのでこれは装備の支給状態の問題ではなく、空挺師団が意図的にミッチェルヘルメットカバーを使用しなかったと思われます。
なお、空挺師団でもミッチェルヘルメットカバーの使用例は一応有るには有るのですが、そのほとんどは佐官級の高級将校に限られています。
なので私は前線の空挺師団将兵の軍装再現としてミッチェルヘルメットカバーを使うのは、明確に間違いだと思っています。

▲ミッチェルヘルメットカバーを着用する空挺師団の幹部。一番右が空挺師団副師団長ホー・チュン・ハウ大佐(1972年)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。